物語のエンジン「原因→心情→反応」の3ステップ連鎖
小説の物語は突き詰めると非常にシンプルな構造で動いています。それは、登場人物の心を動かす「原因→心情→反応」という3ステップの繰り返しです。
- 原因(心が動く要因): 登場人物の感情が動くきっかけとなった出来事・セリフ・状況のことです。「何が起きたのか?」「誰が何と言ったのか?」がこれにあたります。
- 心情(心の内側での動き): 「原因」を受けて、登場人物の心の中で生まれた感情です。「嬉しい」「悲しい」「悔しい」「安堵した」といった内面的な動きを指します。
- 反応(心情相当表現): 生まれた「心情」が、外側に現れた行動・セリフ・表情のことです。「俯く」「拳を握る」「ため息をつく」などといった表現がこれにあたります。
<具体例>
- 【原因】: 親友から「君のそういうところが嫌いだ」と言われた。
- 【心情】: (悲しい、ショックだ、裏切られた気分だ…)
- 【反応】: 彼は何も言い返せず、俯いた。
この3ステップは一度きりで終わるわけではありません。ある人物の「反応」が、次の新たな「原因」となり、物語は雪だるま式に展開していきます。
- 【新たな原因】: 彼が黙って俯いてしまったこと。(先の【反応】が次の【原因】になる)
- 【新たな心情】: 親友は(言い過ぎてしまったか…)と罪悪感を覚える。
- 【新たな反応】: 親友は「…ごめん」と小さな声で呟いた。
このように、物語はこの「原因→心情→反応」の連鎖で成り立っているのです。
答えの見つけ方:解答根拠の黄金ルール
設問で問われるのは、ほとんどが「心情」か「反応(心情相当表現)」のどちらかです。そして、その答えを支える解答根拠は、この3ステップ連鎖の他の2つの要素に隠されています。
ケース①:「心情」が問われた場合
設問例:「傍線部①とあるが、このときの主人公の気持ちを説明しなさい」
この場合、解答の根拠となるのはその心情が生まれた【原因】と、その心情から引き起こされた【反応】です。
- 探すべき根拠:
- 【原因】: なぜ、その気持ちになったのか?(傍線部の直前の出来事やセリフ)
- 【反応】: その気持ちになった結果、どうしたのか?(傍線部の直後の行動や表情)
この2つを本文中から正確に抜き出すことで、「(原因)があったから、(反応)という行動に見られるように、(心情)という気持ちになった」という、揺るぎない答えの骨格が完成します。
ケース②:「反応(心情相当表現)」が問われた場合
設問例:「傍線部②で、主人公が『俯いた』のはなぜか、説明しなさい」
この場合、解答の根拠となるのは、その行動の引き金となった【原因】と、その行動の源泉である【心情】です。
- 探すべき根拠:
- 【原因】: 何が起きたのか?(行動の直前の出来事やセリフ)
- 【心情】: それを受けて、どう感じたのか?(本文中の心情描写)
「(原因)という出来事があり、(心情)という気持ちになったため、(反応)という行動をとった」という論理的な説明が可能になります。
【応用編】表現説明問題の注意点
稀に、「この比喩表現がもたらす効果として、最も適切なものを選べ」といった表現技法に関する問題が出題されます。
このタイプの問題では2つのチェックが必要です。
- 内容の正しさ: その選択肢が説明している内容は、本文の文脈と合っているか?
- 表現技法の正しさ: その選択肢で指摘されている表現技法(例:「直喩」「擬人法」など)は、本当にそこで使われているか?
特に2点目は、国語の知識として表現技法を知らないと判断できません。「直喩(〜のようだ)」「隠喩(メタファー)」「擬人法」「体言止め」といった基本的な表現技法は、別途学習しておく必要があります。
まとめ:論理の鎖で答えを導く
他の記事で紹介した「心情と心情相当表現」への印つけは、この「反応」を可視化する作業でした。設問を解く際には、その印をつけた部分を手がかりに、その前にある「原因」と心の中にある「心情」を探し出す。
この「原因→心情→反応」という論理の鎖を意識するだけで、小説問題は感覚的な作業から根拠に基づいたパズルのような思考ゲームへと変わります。ぜひ、この思考法を次の問題演習から試してみてください。
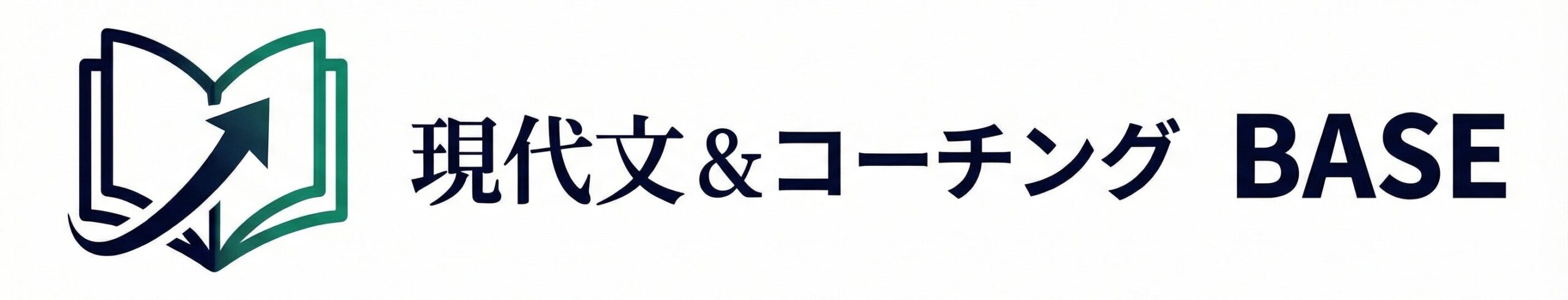
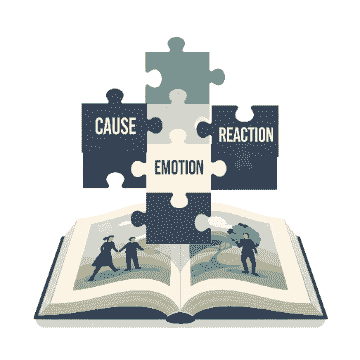


コメント