「現代文はセンスだから、対策しようがない」 「日本語だから、勉強しなくてもなんとかなる」もしあなたがそう考えているなら、断言します。 その思考停止こそが、現代文の点数が伸びない唯一の原因です。
現代文は「感性」を競う芸術ではありません。「論理」を競う情報処理です。 点数が安定しない人には、センスがないのではありません。文章を読む際の「OS(基本動作)」に、致命的なバグ(悪い癖)があるだけです。
今回は、多くの受験生が無意識にやってしまっている「4つの敗因」をあぶり出します。一つでも当てはまったら、そこがあなたの偏差値を爆上げするスイッチです。
原因1:「あなたの感想」ノイズ混入罪
最も多くの受験生が陥る、最大の罠です。
よくある症例
- 文章を読みながら「なるほど、わかる!」「いや、それは違うでしょ」といちいち反応してしまう。
- 選択肢を選ぶ時、「道徳的に正しいほう」や「自分の常識に近いほう」を選んでしまう。
解説
試験で問われているのは「筆者は何と言っているか」だけです。「あなたはどう思うか」は1ミリも問われていません。 自分の主観(感想・常識・経験)というフィルターを通して読むと、筆者の主張が歪んで脳に届きます。結果、出題者が仕掛けた「常識的には正しそうだが、本文には書かれていないひっかけ選択肢」に面白いように釣られます。
処方箋
「自分を殺せ。筆者のイエスマンになれ」:読んでいる間、あなたの自我は不要です。筆者が「カラスは白い」と言えば、その世界ではカラスは白いのです。自分の意見と、目の前の文章を完全に切り離す訓練をしてください。
原因2:「真っ白な問題用紙」は敗北の証
現代文が得意な人の問題用紙は汚く、苦手な人の問題用紙は綺麗です。この差は決定的です。
よくある症例
- 腕を組み、ただ文字を目で追うだけの「受け身の読書」をしている。
- 設問を解く時になって初めて、「あれ、どこに書いてあったっけ?」と本文全体を探し回る。
解説
ただ目で追うだけでは、脳は情報を「風景」としてしか処理しません。論理構造や対比関係が記憶に残らないため、設問のたびにゼロから読み直すことになり、時間切れを起こします。
処方箋
「マーキングは、脳への書き込みだと思え」:汚してなんぼです。「筆者の主張」「具体例」「対比」など、一定のルールで線を引いたり、〇で囲んだりしてください。手を動かすことで、脳はそれを「重要な情報」として認識します。
原因3:「信号無視」の暴走運転
文章には、カーナビのような「標識」が無数に設置されています。それを見落とすのは致命的です。
よくある症例
- 「しかし」「つまり」「たとえば」などの接続詞を、ただの繋ぎ言葉として読み飛ばしている。
- 「これ」「それ」といった指示語の内容を確認せず、雰囲気で読み進める。
解説
接続詞は、文脈の「方向指示器」です。
- 段落冒頭の「しかし」の後には、基本的に「筆者の主張(一番大事なこと)」が来ます。
- 「たとえば」の後には、「読み飛ばしてもいい具体例」が来ます。 このサインを無視するのは、ナビを無視して知らない道を暴走するのと同じ。迷子になるのは当たり前です。
処方箋
「接続詞には、親の敵のように印をつけろ」: 逆接(しかし)、換言(つまり)が出てきたら、必ず〇で囲むなどして立ち止まってください。「ここから話が変わるぞ」「ここからが結論だぞ」と脳に命令を送るのです。
原因4:そもそも「言語」が通じていない
テクニック以前の問題として、武器を持たずに戦場に立っているパターンです。
よくある症例
- 「抽象」「捨象」「形而上」「パラダイム」「アイデンティティ」…これらの意味を、小学生に説明できない。
- なんとなくの雰囲気で言葉を読んでいる。
解説
現代文(特に評論文)は、日常会話とは異なる「論理的な言語」で書かれています。 英単語を知らずに英語長文が読めないのと同様、キーワードの意味(定義)を知らなければ、日本語であっても読解は不可能です。言葉の意味がぼやけていれば、文章全体のピントも合いません。
処方箋
「現代文単語をナメるな」: 市販の『現代文キーワード読解』などを1冊仕上げてください。「辞書的な意味」だけでなく、「評論文でどう使われるか」まで知っておく必要があります。
まとめ:バグを取り除けば、現代文は満点が取れる
現代文は「センス」という魔法ではありません。
- 主観を捨てる
- 手を動かして読む
- 接続詞に注目する
- 語彙を固める
この4つの修正を行うだけで、景色は変わります。 「勉強しても無駄」という言い訳を捨て、今日から「論理的な読み手」へと進化してください。
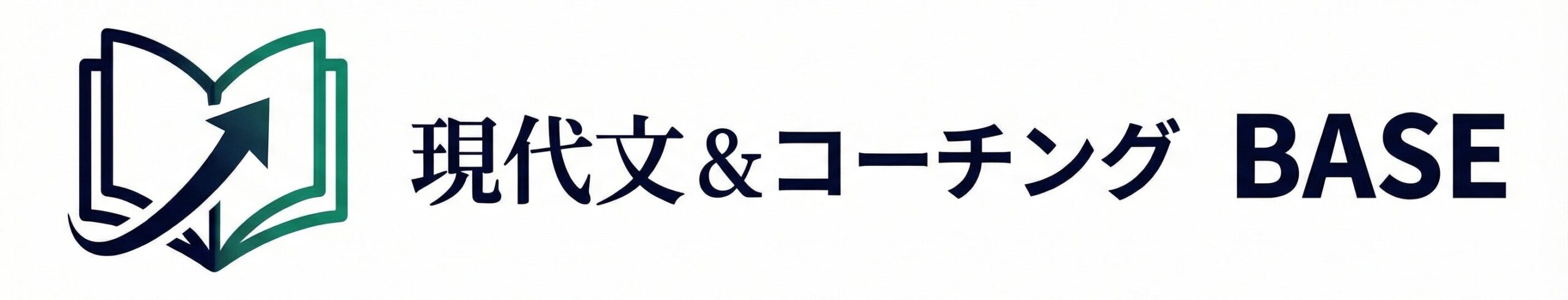
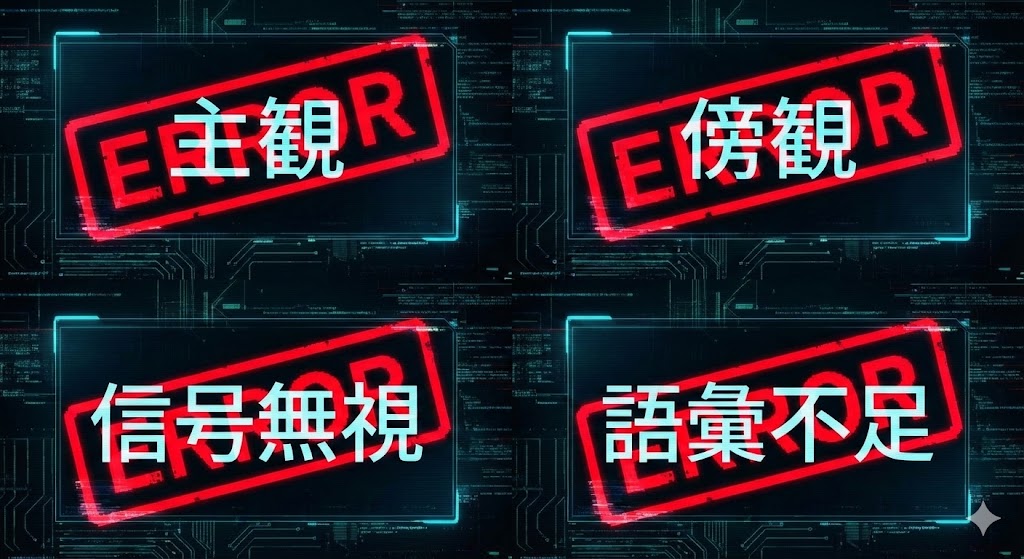


コメント