「隣の席のA君が使っている参考書、なんだか良さそう…」 「ネットでおすすめされていた、新しい参考書を買ってみようかな…」 「この参考書、少しやってみたけど本当に自分に合ってるのかな…」
こんな風に、次から次へと新しい参考書に手を出してしまう「参考書ホッパー」になっていませんか?
本棚に人気の参考書が並んでいくのを見ると、なんだか勉強している気になって安心するかもしれません。しかし、断言します。その習慣こそが、あなたの成績が伸び悩んでいる最大の原因です。
この記事では、なぜ参考書をコロコロ変えることが危険なのか、そしてどうすれば自分に合った1冊を「最強の武器」に変えられるのかを解説します。
大原則:「悪い参考書」は少ない。「悪い使い方」をしている人が多い
まず、大前提として理解してほしいことがあります。確かに、解説の分かりやすさや網羅性など、参考書の質に差はあります。しかし、受験生の間で評判になっているような主要な参考書のほとんどは、合格に必要な知識を十分に網羅しています。「絶対に使うべきではない」というレベルの参考書は、実はそこまで多くありません。
問題なのは、参考書そのものではなく使い方です。 10冊の参考書の1章だけを読んだ生徒と、1冊の参考書を10周した生徒、どちらが合格に近づけるかは火を見るより明らかです。
途中でコロコロ変えるくらいならば、同じ参考書を完璧にすることの方が何倍も価値があります。
なぜ「参考書ホッパー」は成績が伸びないのか?
参考書を頻繁に変えることには、主に3つのデメリットがあります。
- 時間とお金を無駄にする
- 新しい参考書を探す時間、買うためのお金、そしてまた最初からやり直す時間。その全てがライバルに差をつけられている貴重な時間です。
- 知識が断片的になる
- どの参考書も、知識が体系的に身につくように構成されています。しかし、 参考書をつまみ食いするとその体系性が失われ、知識がバラバラの「点」のままになってしまいます。これでは、応用力が求められる入試問題には対応できません。
- 「できる」フェーズに到達しない
- 学力が本当に伸びるのは、参考書を2周、3周と繰り返し、できなかった問題が「できる」に変わる瞬間です。参考書ホッパーは、常に1周目の「インプット」ばかりを繰り返しているため、最も重要な「定着・アウトプット」のフェーズに到達することができません。
後悔しないために。「買う前の検討」がすべて
「1冊を完璧に」という原則を貫くためには、参考書は買う前の検討が何よりも大切です。勢いで買ってしまうのではなく、以下のポイントを必ずチェックしましょう。
- 目的を達成できるか?
- その参考書を終えたとき、どんな状態になっていたいですか?「基礎を固めたい」「演習量を増やしたい」など、目的を明確にすれば選ぶべき1冊もおのずと見えてきます。
- 今の自分のレベルに合っているか?
- 背伸びをして難しすぎる参考書を選んでも、挫折するだけです。「少し簡単かな?」と感じるレベルから始めるのが、結果的に一番の近道です。
- 解説のスタイルは自分に合うか?
- レビュー評価が高いからといって、あなたに合うとは限りません。必ず書店で手に取り、解説を読んでみてください。「この説明、しっくりくるな」と感じられるかが重要です。
例外:参考書を買い替えるべき「唯一のタイミング」
とはいえ、どうしても選んだ参考書が合わない場合もあります。そんな時は、なるべく早めに見切りをつけることが大切です。
- 見極め期間は「1週間」 1週間、本気でその参考書に取り組んでみてください。その上で、「解説が根本的に理解できない」「レベルが絶望的に合っていない」と感じるのであれば、それは買い替えるべきサインです。
重要なのは、ダラダラと何ヶ月も同じ参考書で悩み続けないこと。 1週間で見切りをつけ、新しいパートナーとなる1冊を慎重に選び直しましょう。そして、一度決めたらその1冊を信じて最後までやり抜く覚悟を持ってください。
まとめ
成績は、本棚に並んだ参考書の数で決まるわけではありません。あなたの頭の中に、どれだけ完璧に定着した知識があるかで決まります。
参考書は、あなたの受験勉強を共に戦う「相棒」です。たくさんの相棒をころころ変えるのではなく、心から信頼できる一冊の相棒を選び抜き、共に合格を勝ち取ってください。
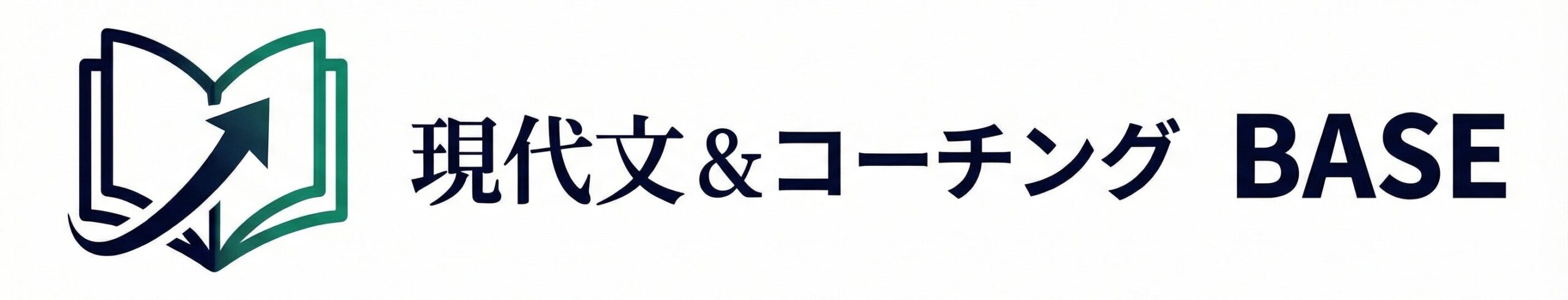

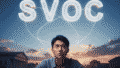

コメント