「計算量が多すぎて時間が足りない…」「誘導が複雑でパニックに…」 多くの受験生がそう嘆く、共通テストの数学Ⅱ・B・C。70分という短い時間で膨大な問題量を完璧に解き切ることは、はっきり言って非現実的です。 高得点を取るために最も重要なのは、「全てを解こう」という完璧主義を捨てること。そして、解ける問題で確実に点数を稼ぐ戦略です。この記事では、そのための具体的な準備と本番での立ち回り方を解説します。(※数学Ⅰ・Aと時間配分以外の対応はほぼ同じです)
試験前の三大戦略:数学力だけでは勝てない
本番で実力を最大限に発揮するには、計算力や公式の暗記だけでは不十分です。共通テスト特有の対策が不可欠になります。
読解力:もはや現代文。問題の意図を掴むべし
共通テストの数学は、問題文が非常に長く、日常生活や社会的なテーマを題材にした一見複雑な設定が頻出します。数式を立てる以前に、「何を問われているのか」「どの情報が必要なのか」を正確に読み解く読解力が不可欠です。
意外に思えるかもしれませんが、これは現代文の読解トレーニングによって鍛えられます。文章の構造を理解し要点を素早く把握する力は、問題の親切な「誘導」にスムーズに乗るための強力な武器となります。
例題暗記:解法の引き出しを増やす
『チャート式』や『Focus Gold』といった網羅系参考書を使った例題の暗記は、対策の基本にして王道です。典型的な問題の解法パターンを瞬時に引き出せるようにしておくことで、試験時間の大幅な節約につながります。特に数Ⅱ・Bは扱う分野が広いため、まずはこの土台を盤石にしましょう。
演習:未知の問題への対応力を養う
例題暗記だけでは通用しないのが共通テストの厳しいところ。必ず見たことがないような切り口の問題が出題され、受験生を揺さぶってきます。
こうした初見の問題に対応するためには、過去問や実践問題集でとにかく場数を踏むことが最も効果的です。様々な問題に触れることで未知の問題への恐怖心を和らげ、持っている知識をどう応用すればよいかを考える思考体力を養いましょう。
問題構成と理想の時間配分
試験が始まったら、以下の時間配分を常に意識してください。時間を意識するだけで、焦りは大きく軽減されます。勿論、得意不得意によって多少は時間配分を調整しても良いです。
| 大問 | 分野 | 配点 | 時間配分(目安) |
| 第1問 | 三角関数 | 15点 | 11分 |
| 第2問 | 指数・対数関数 | 15点 | 11分 |
| 第3問 | 微分・積分 | 22点 | 15分 |
| 第4問 | 数列 | 16点 | 11分 |
| 第5問 | 統計的な推測 | 16点 | 11分 |
| 第6問 | 空間ベクトル | 16点 | 11分 |
| 第7問 | 複素数平面 | 16点 | 11分 |
| 合計 | (第4~7問から3題選択) | 100点 | 70分 |
【戦略のポイント】
- 選択問題は事前に決めておく:本番で問題を見てからどれを解くか迷う時間は非常にもったいないです。「数列」と「ベクトル」、「統計」など、自分の得意な組み合わせを事前に決め、その分野を重点的に対策しておきましょう。
- 必須問題で時間を使いすぎない:第3問は配点が高く計算量も多いですが、ここで時間をかけすぎると選択問題に手が回らなくなります。目標時間を設定し、それを超えそうなら一旦見切る勇気も必要です。
本番の心構え:捨てる勇気を持つ
詰まったら飛ばす
少し考えて解法が浮かばなければ、それはあなたにとっての「難問」です。固執せず、潔く印をつけて次の問題へ進みましょう。1つの問題に時間を溶かすのが最も危険です。
誘導に素直に乗る
共通テストは、(1)が(2)のヒントになっているなど、解きやすいように設問が配置されています。出題者の意図を信じて、流れに乗って解き進めましょう。
完璧な答案は不要
答えさえ合っていれば点数になります。途中式を綺麗に書く必要はありません。計算ミスだけは細心の注意を払いましょう。
まとめ
共通テスト数学Ⅱ・B・Cで成功する秘訣は、完璧を目指さない勇気と、そのための周到な準備です。「読解力」「例題暗記」「実践演習」の三本柱で実力をつけ、本番では冷静な時間配分と「捨てる勇気」で確実に点数を積み重ねていきましょう。応援しています!
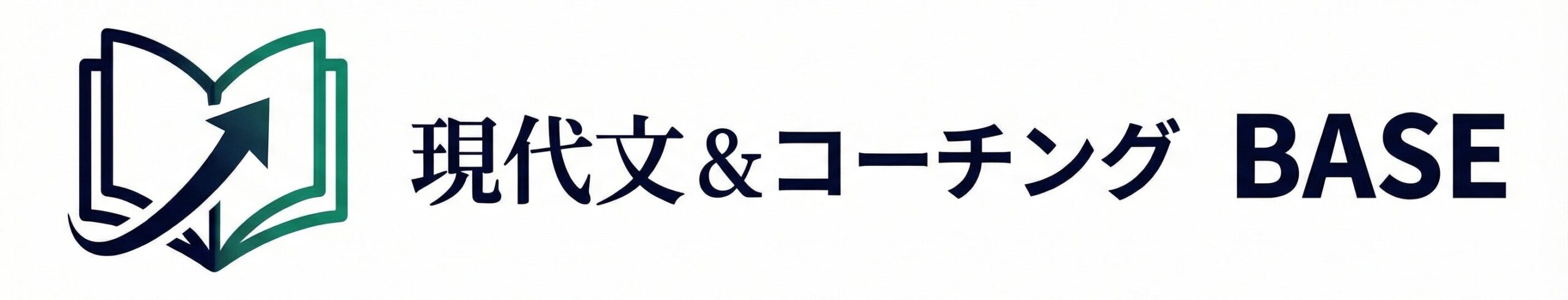
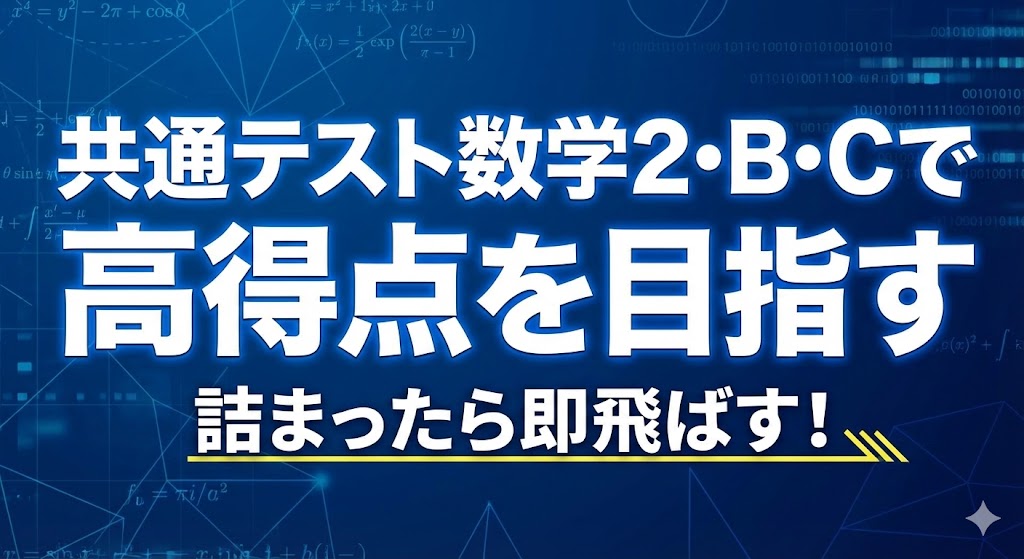


コメント