「高2になったら、そろそろ本気でやらないとヤバイ?」 そう焦る気持ちは分かりますが、ここで高3と同じペースで走り始めると、最も重要な受験学年で確実にガス欠(燃え尽き)を起こします。
高2の役割は「全力疾走」ではありません。高3になった瞬間にトップスピードに入れるための「高性能なアイドリング(暖気運転)」です。 部活の中心として活躍しながら、水面下で着実に爪を研ぐ。今回は、そんな賢い高2生のための「平日3セット(3コマ)の7割運転戦略」を伝授します。
戦略データ:高2生の「アイドリング・ノルマ」設定
高2の間は、以下のノルマを守ってください。多すぎず、少なすぎず、絶妙な「負荷」をかけ続けることがポイントです。
| 項目 | 詳細 |
| 基本単位 | 50分勉強 + 10分休憩 = 1セット |
| 平日目標 | 3セット (学習時間:約2時間30分) |
| 休日目標 | 8セット (学習時間:約6時間40分) |
| 休息日 | 週に1回「半休」(4セットのみ消化) |
| 推奨活動 | 部活(主力)・学校行事・オープンキャンパス |
「高3は平日4セット」とお伝えしていますが、高2はその一歩手前、「3セット」で十分です。
ただし、この3セットだけは、「スマホ封印・音楽なし」の完全な戦闘モードで行ってください。ダラダラやる5時間より、研ぎ澄まされた2時間半が受験の基礎体力を作ります。
なぜ「7割運転」が最強なのか?
真面目な人ほど「高2から毎日5時間!」と意気込みますが、私は止めます。受験はマラソンであり、ペース配分を間違えたランナーは必ず脱落するからです。
理由1:高3の「伸びしろ」を残すため
高2で全力を出し切ると、高3になった時に「これ以上どうすればいいんだ」という閉塞感に襲われます。 「今はまだ7割。本気を出せばもっとやれる」という余力を残しておくことで、高3の春に「セット数を増やす」という明確なギアチェンジが可能になります。
理由2:部活引退後の「切り替え」をスムーズにするため
高2は部活の主力です。ヘトヘトに疲れて帰宅するのが日常でしょう。 その中で「3セットだけは絶対にやる」という習慣がついていると、部活を引退した瞬間、部活に使っていたエネルギーがそのまま勉強にスライドし、驚異的な爆発力を生みます。
平日:部活後にねじ込む「3セット」の配置術
部活で帰宅が20時を過ぎることもあるでしょう。だからこそ、帰宅後の「3セット」をどう配置するかが勝負です。
【平日3セットの配置例】
- 第1セット(帰宅後すぐ):
- 内容: 英語長文、数学の例題。
- 戦略: ここで「1セット分(50分)」を稼いでおくのがプロの技です。
- 第2セット(夕食後):
- 内容: 英語長文、数学の例題。
- 戦略: 最もエネルギーがある時間に、メインの科目を配置します。
- 第3セット(就寝前):
- 内容: 暗記系、その日の復習。
- 戦略: お風呂から上がったらラスト1セット。これを終えれば、心置きなく泥のように眠れます。
休日:土曜は攻めろ、日曜は休め。「8セット」の攻略
休日の目標は「8セット(約6時間半)」です。高3の「10セット」に比べれば余裕があります。 おすすめは、「土曜日にガッツリ稼いで、日曜日は半休にする」スタイルです。
【土曜日のタイムテーブル例(8セット完遂)】
- 08:00 〜 12:00 【午前の部:4セット】
- 部活がない場合、午前中に4つ終わらせます。
- 13:00 〜 17:00 【午後の部:4セット】
- 午後も淡々と4つ。これで計8セット。
土曜日にこれを達成しておけば、日曜日の精神的余裕が違います。
【警告】「半休」は必須。週1回は充電せよ
高2生にとって、休息も立派な戦略です。 週に1回(例えば日曜日)は、「半休(4セットのみ)」としてください。
- 半休のルール: 午前中に4セットだけ集中して終わらせる。
- 午後の特権: 午後は完全にフリー。友達と遊びに行くもよし、溜まったドラマを見るもよし。
「日曜の午後は遊べる」というご褒美があるからこそ、平日と土曜日の学習に身が入ります。このメリハリこそが、高3まで続く強靭なメンタルの源泉です。
まとめ:虎視眈々と「その時」を待て
本記事の戦略をまとめます。
- 高2は「平日3セット・休日8セット」の7割運転でいく。
- 部活で忙しくても、隙間時間を合算して「1セット」稼ぐ。
- 土曜日は攻めて、日曜日は「半休」でチャージする。
- 高3での爆発に備え、今は「習慣の筋肉」だけ鍛えておく。
周りが「まだ受験なんて先だし」と遊んでいる間に、あなたは涼しい顔で「3セット」を積み重ねてください。 その静かなる継続が来年の春、圧倒的な実力差となって現れます。焦らず、腐らず、虎視眈々と牙を研ぎましょう。
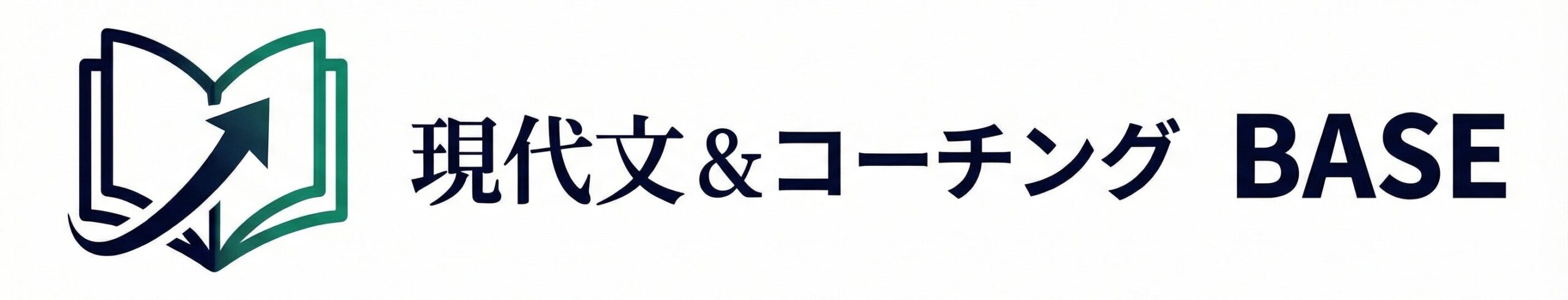
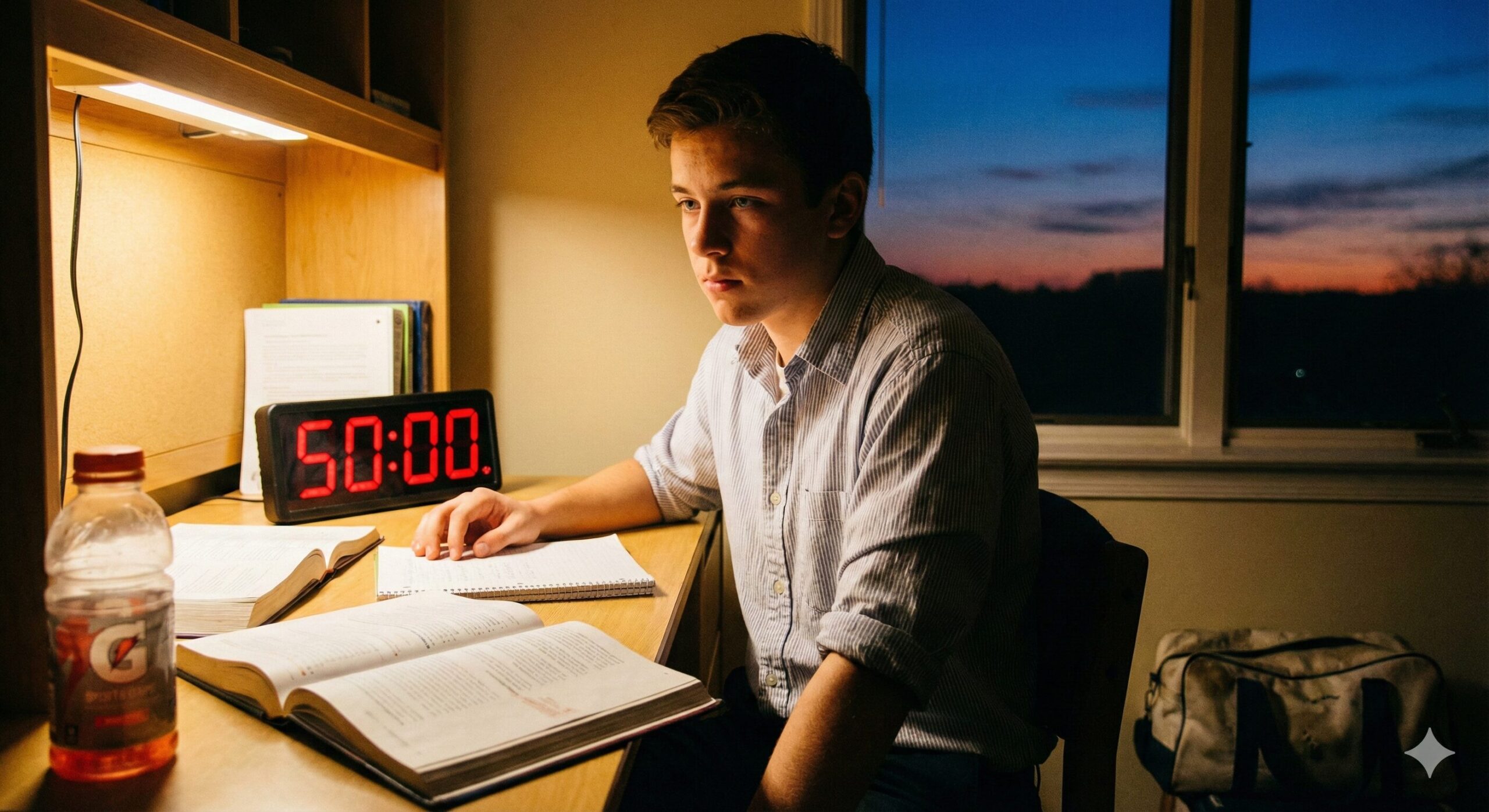


コメント