お子さんの大学受験は、ご家族にとっても一大イベント。親としては「何かしてあげたい」「支えてあげたい」という気持ちでいっぱいになることでしょう。しかし、その良かれと思ってかけた言葉が、かえって子供を追い詰めてしまったり親子関係を悪化させてしまったりすることも少なくありません。
この記事では、受験生のお子さんを持つ保護者の方へ向けて、「言ってはいけないNGワード」と「適切なサポート方法」を解説します。
大前提:過度な干渉は避け、専門機関に任せる意識を持つ
まず、最も重要な前提として保護者の方々が受験勉強そのものに過度に干渉することは避けるべきです。
お子さんの学習内容や進捗管理、志望校選びといった専門的なアドバイスは、学校の先生や塾・予備校の講師といった教育のプロフェッショナルに任せるべきです。保護者の方が直接口出しすることで、かえって子供は混乱し反発を招くことにもなりかねません。
保護者の役割は、あくまで「精神的な支え」と「環境の整備」に徹すること。過度なプレッシャーを与えず、信頼して見守る姿勢が何よりも大切です。
受験生の子供に言ってはいけないNGワード5選
知らず知らずのうちにお子さんを傷つけ、やる気を削いでしまう可能性のある言葉があります。
1. 「〇〇ちゃんはもう受かったらしいよ」「△△くんはすごいね」
【なぜNG?】 他の子供と比較されることは、受験生にとって最も大きなストレスの一つです。競争はありますが、家庭の中でまで比較されると、お子さんは「自分はダメな人間だ」と感じ自己肯定感が低下します。
【代わりに何を言う?】 「あなたはあなたのペースで頑張ればいい」「昨日のあなたより、今日のあなたが頑張っていればそれで十分だよ」
2. 「もっと勉強しなさい」「ちゃんとやってるの?」
【なぜNG?】 子供は自分が一番、勉強しなければいけないことを理解しています。このような言葉は「わかっていることを言わないで」という反発心や、「信用されていない」という不信感を生み出します。
【代わりに何を言う?】 「何か困っていることはない?」「眠い時は休憩してね」など、状況を気遣う言葉をかけるに留めるのが吉です。具体的な勉強のアドバイスは学校や塾の先生に任せてください。
3. 「このままだと浪人だよ」「落ちたらどうするの?」
【なぜNG?】 不安を煽る言葉は、子供の心を萎縮させ、プレッシャーで本来の実力を出せなくする可能性があります。「失敗してはいけない」という強迫観念は、受験を乗り切る上で大きな足かせとなります。
【代わりに何を言う?】 「結果がどうであっても、お父さん(お母さん)は味方だよ」「ここまで頑張ってきたことに意味があるよ」
4. 「〇〇大学じゃなきゃダメ」「〇〇学部が一番良い」
【なぜNG?】 志望校や学部を親が決めてしまうのは、お子さんの主体性を奪い将来の選択肢を狭める行為です。親の期待に応えようと無理をして、燃え尽きてしまうこともあります。
【代わりに何を言う?】 「〇〇大学のこういうところが良いと思うけど、あなたはどう思う?」「色々な大学のオープンキャンパスに行ってみて、納得のいく選択ができるといいね」と、あくまで選択肢の一つとして提示し、最終決定はお子さんに委ねてください。具体的な情報提供や相談は学校や塾の先生に任せてください。
5. 「こんなにお金かけてるのに」「塾代(学費)が無駄になる」
【なぜNG?】 費用面の話は、子供に「親に申し訳ない」「失敗できない」という重荷を背負わせてしまいます。経済的な不安は親が引き受け、子供には勉強に集中できる環境を提供することが大切です。
【代わりに何を言う?】 言葉にする必要はありません。子供には知られないように経済的なサポートをしてあげてください。
受験生の子供への適切なサポート方法5選
NGワードを避けるだけでなく、積極的にできる適切なサポートもあります。
1. 生活環境を整える「影のサポーター」に徹する
勉強に集中できる静かな環境、栄養バランスの取れた食事、規則正しい生活リズムの維持など、お子さんが勉強に専念できる環境を整えることが大切です。家事の分担を見直す、夜食を用意するなど、些細なことでも大きな助けになります。
2. 適度な距離で見守る「信頼」の姿勢
お子さんを信頼し、過干渉せずに見守ることが重要です。勉強の進捗を逐一確認するのではなく、困っている様子があれば「何かあった?」と尋ねる程度にとどめましょう。相談してきたら、じっくりと話を聞き、共感する姿勢を見せることが大切です。具体的な学習のアドバイスは、学校や塾の先生の専門分野です。
3. 体調管理への配慮
睡眠時間、食事、リフレッシュの時間など、お子さんの体調には細心の注意を払いましょう。「疲れているな」と感じたら、無理に勉強を促すのではなく、休憩を勧めたり一緒に軽い運動をしたりするのも良いでしょう。
4. ポジティブな声かけと感謝の気持ち
「頑張っているね」「いつも応援しているよ」「ありがとう」など、お子さんの努力を認め、感謝の気持ちを伝えるポジティブな声かけを増やしましょう。結果ではなく、努力の過程を評価することが、お子さんのモチベーション維持に繋がります。
5. 学校や塾(予備校)との連携を密にする
お子さんの学習状況や精神状態について、学校の先生や塾・予備校の担当者と定期的に情報交換を行いましょう。専門家からの客観的な意見やアドバイスは、保護者の方にとっても非常に参考になります。必要に応じて面談の機会を設けるなどして、お子さんへのサポート体制を構築してください。
まとめ:親の役割は「精神的支柱」
大学受験は、お子さん自身の成長の機会です。保護者の方々は、お子さんの「精神的な支え」となり、「安心して勉強できる環境を整える」ことに徹することが大切です。
過度な期待や干渉はせず、お子さん自身の力と学校や塾(予備校)といった専門機関のサポートを信じて見守ることが、お子さんの合格への何よりの力になります。
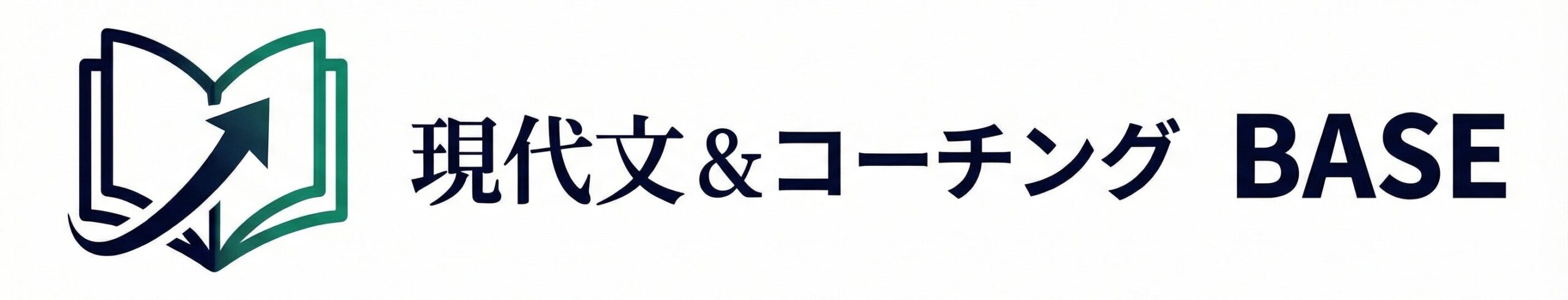


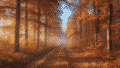
コメント