「共通テストの勉強と二次試験の対策、どっちを優先すればいいんだろう…」受験勉強を進める高校3年生・浪人生の多くが抱えるこの悩み。特に国公立大学を志望する場合、この2つの試験対策のバランスが合否を大きく左右します。
そこで今回は、春から共通テスト本番までの学習期間を6つの時期に分け、それぞれにおける「共通テスト対策」と「二次試験対策」の理想的な学習時間配分を、具体的な理由とともに徹底解説します。
もちろん、これはあくまで一般的なモデルプランです。ご自身の志望校の配点比率や得意・不得意科目に合わせて、柔軟に調整していくことが成功のカギとなります。
大前提:まずは志望校の「配点比率」を確認しよう!
学習計画を立てる前に、必ず確認しなければならないのが、志望校の「共通テストと二次試験の配点比率」です。
例えば、
- A大学: 共通テスト1000点、二次試験2000点(比率 1:2)
- B大学: 共通テスト1000点、二次試験1000点(比率 1:1)
この2つの大学では、取るべき戦略が全く異なります。A大学志望なら二次試験対策に、B大学志望なら両方の対策にバランス良く時間を割く必要があります。
まずは第一志望、そして併願校の募集要項をしっかり読み込み自分だけの「ゴール」を明確に設定することから始めましょう。
【時期別】共通テスト:二次試験 学習時間配分モデルプラン
それでは、具体的な時期ごとの学習時間配分を見ていきましょう。
1. 1学期(4月~7月上旬):基礎固めの時期
学習配分目安 ⇒ 共通テスト:二次試験 = 3:7
この時期の主役は、間違いなく二次試験対策です。
二次試験で問われるのは物事の本質を深く理解し、それを論理的に説明する力。この思考力の土台を作るには時間がかかります。教科書の内容を完璧に理解し、標準的な問題集(例:青チャート、Focus Gold、基礎問題精講など)にじっくり取り組むことで、学力の幹を太く育てていきましょう。
この時期の二次試験対策は、そのまま共通テストの基礎力養成にも繋がります。共通テスト対策は、模試の復習や学校の授業で扱う範囲の確認程度で十分です。まずは焦らず、じっくりと基礎を固めることに専念しましょう。
2. 夏休み(7月下旬~8月):飛躍の時期
学習配分目安 ⇒ 共通テスト:二次試験 = 3:7
受験の天王山とも言われる夏休み。まとまった学習時間を確保できるこの期間も、引き続き二次試験対策を主軸に置きましょう。
1学期に固めた基礎をもとに、応用問題や志望校より少し下のレベルの過去問に挑戦し始めるのがおすすめです。特に、苦手科目の克服に時間を割ける最後のチャンスと捉え、徹底的に向き合いましょう。
共通テスト対策としては、この時期に一度、全教科の過去問を解いてみることを推奨します。これにより、現時点での自分の実力や時間配分の課題、苦手な出題形式などを明確に把握することができます。
3. 9月~10月:二次対策を主軸に、共通テストを意識し始める時期
学習配分目安 ⇒ 共通テスト:二次試験 = 4:6
夏休みで培った実力をさらに伸ばし、二次試験の過去問演習を本格化させる時期です。同時に、少しずつ共通テスト対策の比重を上げていきましょう。
例えば、「平日は二次対策、週末に共通テストの過去問を1年分セットで解く」といったように、計画的に共通テスト演習を組み込んでいくのが効果的です。夏に受けた模試の結果を詳細に分析し、どの科目・分野に時間をかけるべきか戦略を練り直しましょう。
4. 11月:共通テスト対策の比重を高める時期
学習配分目安 ⇒ 共通テスト:二次試験 = 6:4
共通テスト本番まで残り約2ヶ月。この時期から、学習時間の配分を共通テスト対策優位に逆転させます。
過去問演習に加えて、各予備校が出版する予想問題集にも本格的に着手しましょう。共通テスト特有の出題形式や時間配分に身体を慣れさせていくことが重要です。特に、情報や理科基礎、社会などの共通テストでしか使わない科目の対策は、この時期から一気にペースを上げる必要があります。
ただし、二次試験の学力を維持することも忘れてはいけません。毎日30分でも1時間でも良いので、数学の記述問題や英文和訳など、思考力や記述力を要する問題に触れ続ける習慣を維持しましょう。
5. 12月:共通テストモードへ本格移行する時期
学習配分目安 ⇒ 共通テスト:二次試験 = 8:2
いよいよ共通テスト対策が佳境に入ります。この時期は学習時間の大部分を共通テスト対策に充て、総仕上げを行いましょう。
- 本番と同じ時間割で予想問題を解く
- これまで間違えた問題の傾向を分析し、弱点を潰す
- 知識系の科目は、漏れがないか総復習する
など、実践的な演習を繰り返してください。二次試験対策は、これまで解いた問題の復習や学力を維持できる程度の問題演習など、あくまで「感覚を鈍らせない」ための最低限のトレーニングに留めましょう。
6. 1月前半(直前期):最終調整の時期
学習配分目安 ⇒ 共通テスト:二次試験 = 9:1
ここまで来たら、やるべきことはただ一つ。共通テストで自己ベストを叩き出すための最終調整です。
新しい問題集に手を出すのはやめ、これまで使い込んできた教材の復習と、知識の最終確認に徹しましょう。自信を持って本番に臨むことが何よりも大切です。
そして、この時期最も重要なのが体調管理。本番で100%の力を発揮できるよう、睡眠時間をしっかり確保し、生活リズムを整えることを最優先してください。二次試験のことは一旦忘れ、目の前の共通テストに全神経を集中させましょう。
まとめ
| 時期 | 共通テスト:二次試験 | 主な学習内容 |
| 1学期 (4-7月) | 3:7 | 二次対策を主軸に、徹底的な基礎固め |
| 夏休み (7-8月) | 3:7 | 二次対策の演習量を増やし、苦手科目を克服 |
| 9-10月 | 4:6 | 二次過去問を本格化させつつ、共通テスト演習を開始 |
| 11月 | 6:4 | 共通テスト対策の比重を逆転。予想問題にも着手 |
| 12月 | 8:2 | 共通テストモードへ。実践演習を繰り返す |
| 1月前半 | 9:1 | 最終調整と体調管理に徹する |
今回ご紹介した学習時間配分は、あくまで一つのモデルです。大切なのは、あなたの志望校とあなた自身の現状を正確に把握し、「自分だけの黄金比」を見つけ出すこと。
計画通りに進まないことがあっても焦る必要はありません。模試の結果などを参考にしながら、柔軟に計画を修正していく勇気も大切です。
長い受験勉強を戦略的に乗り越えて、志望校合格を掴み取りましょう!
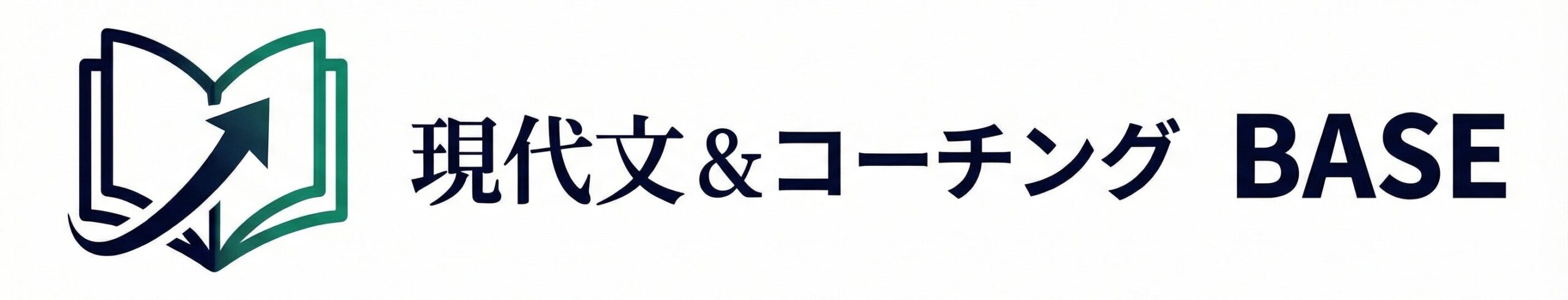

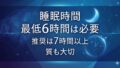
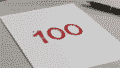
コメント