「うちの子は、もっとできるはずなのに…」「夫(私)に似て、〇〇が苦手なのかしら…」大学受験という大きな壁を前に、お子さんの学力について様々な思いが頭をよぎるのは当然のことです。巷でささやかれる「学力は遺伝する」という言葉に期待したり、あるいは少しだけ不安になったりすることもあるかもしれません。
でも、少しだけ立ち止まってみませんか?最新の研究では、学力における遺伝の影響は約半分と言われています。つまり、残りの半分は「環境」。私たち親が思っている以上に、子どもを取り巻く環境には学力を伸ばすヒントがたくさん隠されているのです。
この記事では遺伝という言葉に囚われず、お子さんがストレスなく学習できる「環境づくり」について、一緒に考えていきたいと思います。
「遺伝」はただのスタート地点。可能性を広げるのは「環境」です
行動遺伝学という分野の研究によると、学力に影響を与える要素は、ざっくりと以下のように言われています。
- 遺伝の影響:約50~60%
- 家庭環境(共有環境)の影響:約30%
- 友人や学校など(非共有環境)の影響:約10~20%
「やっぱり遺伝が半分も…」と思われるかもしれませんが、見方を変えれば約半分の要素は後から変えられる、ということです。遺伝はあくまで「得意・不得意の傾向」や「物事の吸収のしやすさ」といったスタート地点のようなもの。その後の伸びしろは、家庭という「土壌」と、友人や先生といった「水や光」が大きく関わってきます。
大切なのは、お子さんが持つ個性や特性を理解しつつ、それを最大限に伸ばせる環境を整えてあげることです。
家庭でできる「ストレスフリーな環境づくり」のヒント
受験期は、お子さん自身が最も大きなプレッシャーと戦っています。家庭は、彼らにとって唯一心から安心できる「安全基地」であるべきです。学力を伸ばすための特別な教育や過度なプレッシャーではなく、日々の小さな心がけが、お子さんの心を支え、結果的に集中力を高めます。
- 親自身がリラックスする時間を持つ:保護者の不安やイライラは驚くほど子どもに伝わります。保護者様自身が趣味の時間を楽しんだり、友人とお茶をしたりして心に余裕を持つことが家庭の穏やかな雰囲気につながります。
- 「勉強しなさい」より「今日もおつかれさま」:口うるさく言うよりも、「いつも頑張っているね」という承認の言葉や温かい飲み物を用意してあげるなどの行動が、お子さんの孤独感を和らげます。
- 結果ではなく「過程」に注目する:模試の判定や点数に一喜一憂するのは、親も子も疲れてしまいます。「今回はこの分野を頑張ったんだね」「毎日コツコツ続けていてすごいね」と、努力の過程を具体的に褒めてあげてください。
- 心地よい学習スペースを一緒に作る:静かな環境が好きか、少し生活音がする方が集中できるか。机の周りの整理整頓を手伝ったり、お気に入りの文房具を揃えたり、お子さんの好みに合わせた空間を一緒に作ってみたりするのも良いでしょう。
「非共有環境」を豊かにするサポート
お子さんの世界は家庭だけではありません。友人や先生、塾の仲間、部活動など、家庭の外での経験(非共有環境)もまた大きな影響を与えます。
- 子どもの人間関係を信じて見守る:友人との他愛ないおしゃべりや時には息抜きに遊ぶ時間も、受験期を乗り越える上での大切な潤滑油になります。心配になる気持ちを少しだけ抑えて、お子さんの人間関係を尊重し見守る姿勢も大切です。
- 「ナナメの関係」を大切に:親や先生といったタテの関係だけでなく、少し年上の先輩や塾のチューターさん、親戚など、「ナナメの関係」の大人がいると、親には言えない悩みも相談しやすくなります。
- 時には勉強場所を変えてみる:いつも自室で勉強しているなら、図書館や地域の学習センター、カフェなどで勉強することを提案してみるのも一つの手です。環境を変えることで気分転換になり、良い刺激を受けることもあります。
最後に:保護者にできる最大のこと
大学受験は、お子さんの人生における大きな挑戦です。遺伝的な素質がどうであれ、それを開花させるのは、本人の努力と彼らを取り巻く環境です。
私たち保護者にできる最大のことは、「何があっても、あなたの味方だよ」という絶対的な安心感を与えること。そして、お子さんが自分の力を信じて、健やかに受験期を走り抜けられるように穏やかな環境を整えることなのかもしれません。
遺伝という言葉に一喜一憂せず、目の前で頑張っているお子さんの一番の応援団でいてあげてください。
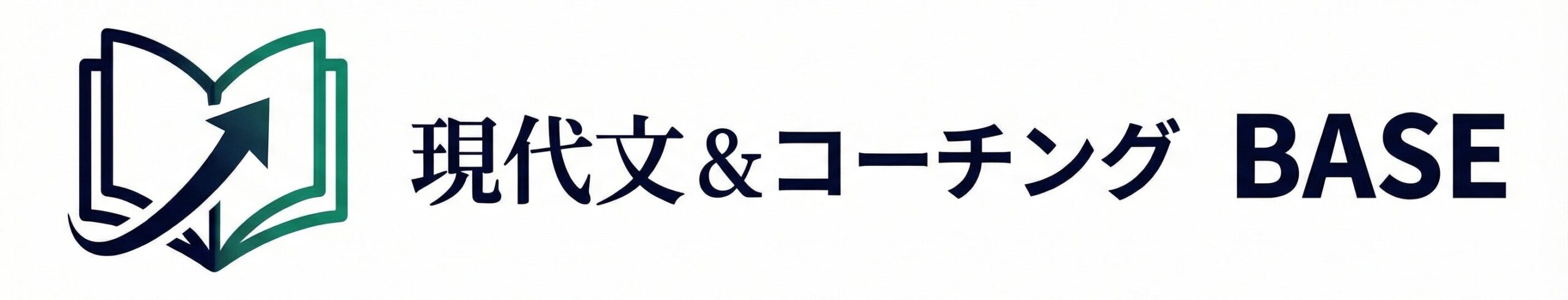
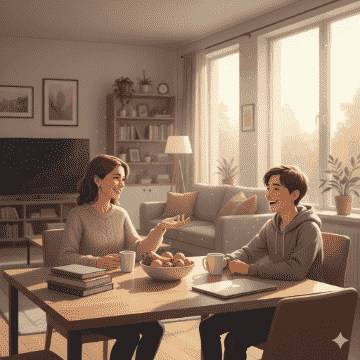
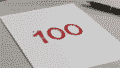

コメント